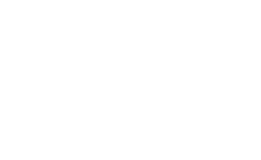図解ー勝共理論 3
図解・勝共理論 32 唯物弁証法 5
目的の下での相互関連性
事物は個と全体の二重目的もつ
宇宙のすべての事物は、目的を中心として相互に関連し合っているというのが統一思想の見解です。
たとえば人体は60兆の細胞からできていますが、それらの細胞は組織、器官、人体を形成しながら、人体の生命を維持するという目的の下に相互に関連し合っています。この細胞相互の関連性は決して偶然的なものではなく、精密な設計図に従った合目的的なものです。
これと同じように、宇宙は一つの巨大な有機体あるいは生命体です。その中で無数の星は一定の目的の下で相互に関連し合って宇宙を形成しています。動物と植物が酸素と炭酸ガスを交換しながら相互に関連しているのも、そうすることによって互いに生存を維持するためです。生物はすべて生存の維持という目的の下での相互関連性をもっているのです。
このように宇宙の相互関連性は目的を中心とした相互関連性と言えます。宇宙に目的を認めれば、宇宙が現れる前にその目的を立てた意思(宇宙意志)があったこと、したがってその意志の所有者すなわちその主体としての神(創造主)が存在していることを認めざるを得ないでしょう。
このことを認めたくないのが唯物論弁証法です。それで相互関連性について目的を抜きにして法則だけで説明しようとするのです。しかし法則は目的(創造目的)を前提としたものであって、目的性のない法則性はあり得ません。したがって目的性のない相互関連性もまたあり得ないのです。
個体と相互関連性との関係について統一思想は、すべての事物は各々、神の二性性相に似た属性をもった個体すなわち個性真理体であると同時に、他の個性真理体と関係を結ぶ個体すなわち連体であると見ます。
各個体は個性真理体としてその個体特有の性質(個別性)を常に維持しながら、連体として互いに影響し合っているのです。これは宇宙の星も人体の細胞も同じです。
すべての事物(個体)は個別性と連体性を統一的に担っており、この両面性を必ず備えています。それは各個体が二重目的、すなわち個体目的と全体目的をもっているからです。個体目的は個体自身の生存を維持し発展しようとする目的であり、全体目的は他者または全体の生存・発展に貢献しようとする目的です。
唯物弁証法は相互関連性を強調しながら、形而上学に対して事物を個別的、固定的にとらえると言って批判しましたが、唯物弁証法も形而上学も、ともに事物を一面的にとらえ、連体性と個別性の統一として把握していないという点では同じなのです。
図解・勝共理論 33 唯物弁証法 6
「変化」のみ強調し致命傷に
ルイセンコによるソ連農業の悲劇
事物を相互関連性とともに変化でとらえ、変化のみを強調するのがマルクス主義の特徴です。
たしかに世界は不断に運動・発展しています。しかし、だからといって事物に不変の面はなく、変化だけがすべてなのでしょうか。この変化だけしか見ないマルクス主義の誤りはルイセンコ学説で証明されています。
ルイセンコ(1898~1976)は旧ソ連の生物学者です。事物の変化のみを強調する唯物弁証法を生物学にも適用して、スターリンの絶大な信頼を得てソ連農業を指導しました。
彼はメンデル・モーガンの遺伝学説に公然と異議を唱えました。遺伝学説は形質が遺伝子によって子孫に伝えられるといい、遺伝子の不変性や種の不変性を主張しています。これは事物の絶えざる変化や発展のみを主張する唯物弁証法とは相容れません。ルイセンコはこれをブルジョア的・形而上学的学問として攻撃し、ソ連国内の生物学者を多数、粛清しました。
彼は秋まき小麦を春化処理によって春まき小麦に変える実験を通じて、環境によって生物の遺伝性が規定されることを明らかにしたと主張し、遺伝学説を真っ向から否定したのです。
つまり、小麦には秋にまく2年生と春にまく1年生があり、秋まき小麦のほうが収穫量が多いのですが、秋まきは冬の冷害にやられやすいという問題があります。そこでルイセンコは、秋まき小麦の種子を一定の期間冷蔵して(つまり、環境によって形質をかえ)春にまけば、その麦は実をむすび大収穫を得られるはずと、主張したのです。
これをスターリンが後押しして、1930年代から実に30年間にわたって全ソ連の農業分野でルイセンコ学説が大手を振ってまかりとおったのです。その結果は「ひでりに強い作物も寒さに強い作物も選抜できず、ソビエトの深刻な農業不振につながった」(メドベージェフ)のです。
変化のみを強調する唯物弁証法の間違いをルイセンコ事件は証明しているでしょう。
なぜそこまで変化にこだわるのでしょうか。その理由をスターリンは「世界は不断の運動と発展のうちにあるならば、資本主義制度を社会主義制度にとりかえることができる」と率直に述べています。
つまり、唯物弁証法は革命を正当化するための理論にほかならないのです。ここでも共産主義の党派性が浮き彫りになっていると言えるでしょう。
図解・勝共理論 34 唯物弁証法 7
自己同一性と変化は不可分に
目的を中心に存在する事物の必然
ソ連の生物学者ルイセンコは1930年代に唯物弁証法を生物学に持ち込み、スターリンの庇護のもと、環境によって遺伝性が規定されると断じてソ連農業を破綻させました。この誤りがソ連で確認されたのは1970年代のことでした。それほど唯物弁証法は金科玉条視されてきたのです。
では、統一思想は変化をどう見るのでしょうか。
統一思想では、すべて事物において不変と変化、自己同一性と発展性は不可分に統一されていると見ます。すなわち、すべて事物は自己同一性を保ちながら変化、発展しているのです。
実際、植物も動物も人間も、みな不断に変化、発展(成長)しながらも、おのおの不変なる特性を維持しています。たとえばリンゴの木は成長(変化)しながらも、リンゴの木であり続けています(不変)。あるいは馬も成長しながら馬という動物であり続けているのです(不変)。
つまり、リンゴはリンゴの木として生存し、リンゴの実をみのらせるという目的を中心として存在しているので、自己同一性を保ちながら変化や発展しているのです。馬も同様です。
ところが、形而上学は自己同一性(不変)のみを扱い、唯物弁証法は発展性(変化)のみを扱っているのです。いずれも一面的にしか物事をとらえていないことになるわけです。
ところで、ヒトゲノムの遺伝子暗号の全解読が20世紀末にほぼ完了しました。このヒトゲノムについて筑波大学名誉教授の村上和雄氏は「この膨大な情報が、極微の空間にどのようにして書き込まれたであろうか、という不思議な感慨にとらわれている」と述べています(『サムシング・グレート』の不思議=産経「正論」2002年4月7日)。
人の細胞は約60兆個。その一つ一つが命をもち、この集合体が毎日、喧嘩もせずに見事に生きている、この大自然の偉大な力「サムシング・グレート」によって私たちは生かされている、と村上氏は言うのです。
その細胞は、さまざまなケースがありますが、およそ数カ月で?死滅?し、新たな細胞に変わっていくとされます。細胞レベルではまったく別の細胞に変わっているのですが、人間レベルで見れば人間として何か別のものに変わったわけではけっしてありません。あくまでも自己同一性を保っています。つまり自己同一性を保ちつつ変化しているのです。
宇宙の相互関連性と変化は目的を中心とした相互関連性と変化なのです。その目的を立てた意志(宇宙意志、村上氏がいう「サムシング・グレート」)があったこと、つまり神の存在を認めない限り、相互関連性も変化も説明できないのです。
ここに唯物弁証法の決定的誤りがあると言えるでしょう。
図解・勝共理論 35 唯物弁証法 8
「統一と闘争」という詭弁
用語の策略で革命を正当化する
唯物弁証法はすべての事物は矛盾によって、あるいは対立物の統一と闘争によって発展すると言います。ここで言う統一と闘争とは、先に統一があり後に闘争が起こるとの意味ではありません。統一と闘争が同時的に現れることを意味します。
ヘーゲル弁証法の場合は、二つの契機(要素)が同一の基盤(同一性)の上で互いに向き合っている状態を「対立」と言い、「対立」がより先鋭化した状態を「矛盾」と言いました。
この「矛盾」は一つの要素が他の要素を排斥(否定)しながらも相互の関係を維持する状態で、そこには他方を打倒するとか、絶滅させるといった意味はありませんでした。ところが唯物弁証法は「対立」にも「矛盾」にも一方が他方を打倒、絶滅させるという意味が加えられています。
つまり、対立物の統一と闘争によって発展すると言いながらも、闘争に重きを置き、統一は相対的であって闘争のみが絶対的であるとするのです。こう主張するのは対立物の闘争のみが暴力革命を合理化できるからです。
にもかかわらず統一を言うのは、血みどろの闘争を嫌い平和的な社会改革を願う人民大衆の目をくらますためです。「統一と闘争」という概念で「平和的な闘争」もありえるといった印象を大衆に与えて彼らを動員し、暴力革命に利用しようとする策略です。
たとえば毛沢東は矛盾には敵対的矛盾と非敵対的矛盾とがあるとして次のように言いました。
「われわれは、敵対とは、矛盾の闘争の一つの形式であって、矛盾の闘争の普遍的な形式ではない、と答える。…一部の矛盾は公然たる敵対的性質をおびているが、他の一部の矛盾はそうではない。事物の具体的な発展にもとづいて、一部の矛盾はもと非敵対的であったものから敵対的なものに発展し、また一部の矛盾はもと敵対的であったものから非敵対的なものに発展する」(『矛盾論』)
毛沢東の敵対と非敵対の概念はレーニンが統一と闘争を同時的であるとしたのに対して同時的ではありませんが、いずれにしても対立物の統一と闘争、あるいは敵対的矛盾と非敵対的矛盾と言って、どちらの意味にも取れるように用語の意味を複雑化させ、用語上の策略を弄しているのです。
これは一般大衆の判断力を混乱させて、彼らの目的(暴力革命)を成就するためのものなのです。彼らの意図は統一にあるのではなく、どこまでも対立物の闘争、敵対的矛盾にあることを忘れてはなりません。
図解・勝共理論 36 唯物弁証法 9
磁石は対立物ではない
N極とS極は磁場形成の相対要素
マルクス弁証法のいう対立物とはいったい、何を指すのでしょうか。
エンゲルスは「(弁証法は)自然全体を支配するものであり…もろもろの対立における運動の反映にすぎない。そしてそれらの対立こそは、そのあいだの不断の闘争により、また結局はそれらがおたがいに移行しあうかあるいはより高次の形態に移行することによって、まさに自然の生命を条件づけている」(『自然の弁証法』)と言いました。
そして、その具体例として磁石を取り上げ、磁石を二つの部分に分けても各々の部分に必ず対立物(矛盾)であるN極とS極が現れるとしました。
はたしてエンゲルスが言うように両極は対立物でしょうか。
小学校の理科の実験でご存知のように、一つの磁石の周りに鉄の粉をふりまけば、鉄粉はN極とS極を結ぶような曲線を描いて並びます。これはN極とS極が互いに引き合っているから起こる現象であって、対立しているから起こるのではありません。
N極とS極は引き合う(いわば互いに相手を必要とする)関係であって反発、対立してはいないのです。
磁石を半分に分割して、二つの極、つまりN極とS極に分けようとしても、分割された磁石はまたN極とS極をもった磁石になりますが、これは磁石が必ずN極とS極を対でもっていて「磁気双極子」を構成しているからです。
つまりN極とS極は対立する要素ではなく、一つの磁場を形成する相対的な要素であり、したがって対立物ではなく相対物と言えます。
N極とN極、あるいはS極とS極を向かい合わせて、そこに鉄粉をまけば、鉄粉は互いに相手の極から離れていくような曲線を描きます。これは二つの極が反発するからです。ここだけを取り上げれば一見、対立物に見えます。
しかし、これは反発しないとそもそもN極とS極の相対関係が作れないからであって、いわば磁石として存在するための補完作用と言えます。しかもN極とS極の引き合いは発展とは関係のない、二つの要素の調和した静的な現象にすぎません。したがって磁石は対立物ではありません。
エンゲルスは「両者が対をなしていることは、両者が対立していることにのみ成り立つ」(同)と述べていますが、これは自然界における相対物や調和をすべて「対立」という言葉に置き換えたにすぎません。
図解・勝共理論 37 唯物弁証法 10
2つの機能を対立物と偽る
蠕虫の口と肛門は協力関係に
エンゲルスは対立物の例として、磁石とともに蠕(ぜん)虫を取り上げ次のように言います。
「蠕虫を切断すると、正極のところではものを摂取する口をそのままもちつづけ、他端のところでは負極を形成して排出用の肛門をもつようになる。ところがもとの負極(肛門)は正となり、口となって、新しい肛門あるいは負極が傷口のところに形成される。正から負への転化である」(『自然の弁証法』)
磁石は切断すると切断面の各々の部分に必ずN極とS極が現れ、元の極はそのままです。これに対して蠕虫を切断すると、切断面の各々の部分が肛門となり、もとの肛門が口になります。
蠕虫の仲間で、なじみがあるのはサナダムシでしょう。サナダムシは一部でも体中に残ると、再びサナダムシになるので、虫下しで完全に出さねばなりません。エンゲルスがいうのはこの「再生」のことです。
一般に原始的な生物ほど再生能力が高く、代表的な例としてミミズやヒドラ、イモリなどがあげられます。とりわけプラナリアという扇形動物の仲間は体を百分の一に切り刻んでも本来の形に再生するといわれ、生物学でよく扱われます。
前述のエンゲルスの説明によれば、切断されて「再生」した蠕虫は切り口が肛門になるので、もとの肛門が口になる「正から負の転化」が起こるというのです
しかし、虫の再生がすべてそうなるわけではありません。プラナリアの場合、真っ二つに切ると頭のほうの上半分は頭がそのままで切り口が肛門、下半分のほうは肛門がそのままで切り口が頭になり、「正から負の転化」は起こりません。一般的な再生はこうなっています。
ところが頭に極端に近いところで切断すると、頭が生えてくる場合があり、これを「再生の[場]の影響」と呼びます。「ここが頭である」との情報が頭に近いほうに強いために頭が生えてくるとされるのです。
それはさておき、そもそも口と肛門は対立物なのでしょうか。
口は食べる機能を、そして肛門は排泄の機能を果たし、互いに協力しあいながら虫の体全体を生かしており、そこには何の対立もありません。両者は虫を生かし成長させる共通目的のもとに機能しているのです。
仮に口は食べても肛門が排泄しないとか、肛門が排泄しても口が食べないとすれば、口と肛門が対立し合っているといえますが、そんなことになれば虫は死んでしまうでしょう。つまり、対立物としては存在すること自体が不可能なのです。
エンゲルスは2つの機能を対立物と偽っているのです。
図解・勝共理論 38 唯物弁証法 11
飛矢静止論で「運動」を矛盾に
時間・空間を無視した非科学的主張
エンゲルスは矛盾(対立物)の例として物体の運動をあげます。
「運動そのものが一つの矛盾である。すでに単純な力学的な場所の移動ですら、一つの物体が同一の瞬間にある場所にありながら同時に他の場所にあること、すなわち同一の場所にあるとともにそこにないということがなければ、行われえない。しかも、かような矛盾を不断に定立しながら同時に解決していくことが、まさに運動なのである」(『自然の弁証法』)
これはゼノンの「飛矢静止論」について述べたものです。ゼノン(古代ギリシャ・エレア派の哲学者)は、もし矢がある瞬間にある点にあるとすれば、矢はその点に静止しており、もしある瞬間にどの点にもないとすれば、矢はどの点をも通過せず運動したのではないとし結局、矢は静止していると論じました。
これに対してエンゲルスは「運動している物体はある瞬間にある場所にありながら同時にない」と説明してゼノンのパラドックスを解決したと言います。つまり、物体は静止しながら運動する、まさに運動は矛盾(対立物)だと言うわけです。
そうでしょうか。そもそもゼノンの飛矢静止論は「飛んでいる矢がある点にあるとき」と、空間のもたない数学的な点を論じており、これは現実には存在しません。
実際の運動は時間・空間の中で行われますので、物体の運動する速度(V)は空間中の距離(S)を時間(T)で割ったもの、V=S/Tと表されます。
つまり、物体の運動は一定の時間、一定の距離で捉えなくてはなりません。位置だけあって空間のない点(数学的な点)で物体の運動を論ずることはできないのです。
ある点(ある場所)における物体の運動は、その場所がいかに微少であっても、それは一定の空間における運動であり、また、ある瞬間における運動は、その瞬間がいかに短くても一定の時間における運動なのです。
したがって物体が運動に際して静止しながら同時に運動する(ある場所にありながら同時にない)ことはあり得ません。運動している物体の位置は時間の函数で表されるので、ある瞬間にはある場所が対応し、別のある瞬間は別のある場所が対応しているのであって、ある瞬間に同時に二つの場所にあるというエンゲルスの主張はあり得ないことなのです。
運動している物体を正確にいうと、物体は?静止することなく空間を通過している?ある瞬間に、ある場所に運動しつつ「ある」のです。
ここでも唯物弁証法の間違いは明白です。