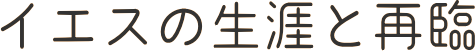第六章 奇跡と信仰
み言と癒し
韓国動乱のさ中,釜山は避難民でごった返していました。ひとりの若い女性伝道師が、釜山の山の中腹に変わった青年がいると聞いて、訪ねてみることにしました。石を積んで土を塗り、屋根はダンボールを被せただけの,馬小屋よりもひどいものでした。中は二畳ほどで、土に油紙を敷いただけの床です。人がこのような所で生まれて死ぬなら、どれほどの恨みが残るだろうか、と彼女は思ったほどでした。
青年は彼女が来ることを予期していたように、二千人の聴衆を前にしているような大声で語りだしたのです。その迫力に圧倒されて,宣教師は黙って聞いているしかありませんでした。話は神の創造から始まり,韓国にメシヤが来るという壮大なものでした。終わりに青年は祈祷しました。それはキリスト教の伝道師がかって聴いたこともない、心が震えるような祈祷でした。青年と共に神がおられて、涙ながらに祈るのでした。
しかし一歩外に出て現実に戻ると,彼女の心に不信の思いがわいてくるのでした。彼女の教会では何百人という信徒が集まるのに、そこは吹けば飛ぶような小屋で、聴衆はただ一人きりです。すると彼女の足は、地面に張りついたように動かなくなるのです。不信の思いを払うと,足は前に進むのでした。
そんなことが何度かあって後、彼女はふもとの木の下で祈りました。「神様、もう決してあの青年の所には行きません。今日は、お別れの挨拶をしてきます」
小屋の前で,青年は怖い顔をして立っていました。そして彼女の祈りが聞こえていたかのように、その内容をすべて言い当てるのです。彼女はついに屈服して,釜山での文師の初めての弟子になったのでした。神秘的な霊力とみ言によって,彼を師と仰ぐ人が次第にふえてゆきました。
ヨハネの第一章にも,同じような事があります。ピリポがナタナエルに、メシヤに出会ったと告げると,彼は「ナザレからなんのよいものが出ようか」と信じなかったのです。ところがイエスに「いちじくの木の下にいるのを見た」と言われ、「ほんとうのイスラエル人である。その心に偽りがない」と心を見抜かれると、イエスをメシヤとして信じたのでした。ペテロがイエスに声をかけられて、すぐに網を捨てて従ったのも、イエスの霊的な力に打たれたからでしょう。しかし無学な漁師や群集は,イエスのみ言を理解するよりも、病気を癒すイエスの霊力に引かれて集まってきたのでした。
イエスが山を下りると、おびただしい群集がついてきました。マタイ第八章以下は、イエスの癒しと奇跡の物語です。イエスはらい病人をきよめ,百卒長の僕の中風を癒し、ペテロのしゅうとの熱病を癒します。
イエスの評判はたちまちガリラヤ湖の周辺の村や町にひろまり、群集が押し寄せてきました。イエスが弟子たちと舟に乗られたときのことです。突然,激しい暴風が起り、舟は波にのまれそうになりました。イエスは起き上がって、風と波を叱りつけると、あらしは静まったのです。「この方はどういう人なのだろう」弟子たちは感動したのでした。
イエスの一行が向こう岸に着くと、悪霊につかれた二人の者が、墓場から出てきました。彼らは悪霊の現象によって、凶暴な狂人になっていたのです。
「神の子よ、わたしどもを苦しめるのか」と悪霊は叫び、追い出すなら豚の中に入れてくださいと願ったのです。イエスが「行け」と言われると、悪霊は豚の中に入り、豚の群れはなだれを打って海に落ちました。豚の飼い主は、さぞ驚いたことでしょう。
イエスの癒しを見てみると、ほとんどが悪霊払いであったことが分かります。医師でもあった李相軒先生の霊界通信によれば、病気の七,八割は悪霊による現象だということです。ですからイエスのような霊能力のある人には、悪霊払いによる癒しは不可能な事ではないのです。現代においても韓国の聖地清平においては、霊界からの協助によって悪霊を払い、難病が治癒する事が起っているのです。またそこでは、み言と祈祷による修練会が行われています。その人間の心が相変わらず悪に相対しているなら、悪霊は再び入ってくるのです。ですから悔い改めと、み言と信仰生活が不可欠なのです。イエスはこのように語っています。
「汚れた霊が人から出ると、休み場を求めて水の無い所を歩きまわるが見つからない。そこで、出てきた元の家に帰ろうと言って帰って見ると、その家はあいていて、そうじがしてある上、飾りつけがしてあった。そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つの霊を一緒に引き連れてきて中にはいり、そこに住み込む。そうすると、その人ののちの状態は初めよりももっと悪くなるのである。よこしまな今の時代も、このようになるであろう」(マタイ12:43)
奇跡と癒しによる伝道には限界があることを、イエスは知っておられたのです。
罪を許す権威
さて、イエスが再び元の町に戻ると、今度は寝たきりの中風の病人が連れてこられました。イエスは彼らの信仰を見て、「子よ、あなたの罪は許された」と言われました。すると律法学者たちは、心の中で言ったのです。「この人は神を汚している」
イエスは彼らの心の動きを見抜いて言われました。
「なぜ、心の中で悪いことを考えているのか。人の子が地上で罪を許す権威をもっていることを知らせるために。起きて,床をあげて家に帰れ」
すると病人は歩いて帰ったのです。人々は驚き恐れ,神をあがめたのでした。
らい病人,盲人、不具者たちは、その罪の現れと考えられていました。彼らは社会から差別され、病苦と共に精神的な、二重の苦しみを受けていたのでした。イエスから「あなたの罪は許された」と言われた時、彼らは少なくとも精神的な苦しみからは解放されたのです。イエスを神の子と信じて、彼によって許された瞬間、たといらい病で欠落した鼻が元に戻らなくても、彼らは確かに「救われた」のです。
しかしながら律法学者、パリサイ人にとって、罪を許す権威は神にのみあるのです。人間が人間の罪を許すとは、傲慢そのものであり、はなはだしく神を汚す言葉です。問題はイエスがメシヤか、偽メシヤかということにかかっているのです。メシヤが来る前に、まずエリヤが来なければなりません。エリヤが来ていない以上、メシヤを自称する者は偽メシヤです。しかもイエスは祭司でも学者でもなく、大工の息子に過ぎません。その上、律法を軽視しているという噂です。悪霊を追い出し、癒しの業をするというが、律法ではまじないのたぐいは禁じられているのです。それともイエスは狂人か。あれは悪霊が悪霊を追い出しているに違いない、彼らはそう考え、イエスを断罪する側にまわったのでした。
イエスが旧約時代のモーセと同じみ言を語っていたなら、祭司、律法学者、パリサイ人たちから、あれほど反対されることはなかったでしょう。イエスは律法学者のようには語らなかったのです。人間の生き方を、根本的に変革するみ言を語ったのでした。変革者は常に、既成勢力から反対を受けるものです。事情は文師の場合も同じでした。神父や牧師のようにみ言を語ったなら、文師があれほど既成教会から攻撃、反対されることはなかったでしょう。変革者は常に「世を惑わす者」であり、異端とされたのです。
弟子たちがイエスに懸ける思いと期待はさまざまでしょうが、彼らは現状を打破する夢を抱いた青年たちでした。彼らは何もかも捨てて、イエスに従って行ったのです。
「わたしに従ってきなさい」とイエスに言われたとき、その弟子は父が亡くなったばかりでした。「まず父を葬りに行かせてください」と彼は言いました。
「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、出て行って神の国を告げひろめなさい」(ルカ9:60)とイエスは答えました。
父を葬ることは息子の務めであり、また親族のすべきことです。しかしイエスは、その息子の務めを放棄して従えというのです。人の世の常識を捨てよということです。そして生きて葬式を出す親族を、イエスは死人と呼んだのです。神との因縁が切れた人間は、霊的には死んでいる人間ということです。イエスの思想とみ言は、俗世間の常識と価値観とは、真っ向から対立するものであったのです。
「まず家の者に別れを言いに行かせてください」(ルカ9:61)と言う弟子には、イエスはこう答えるのです。
「手をすきにかけてから、うしろを見る者は、神の国にふさわしくないものである」
愛と許しの人イエス
神の国は心の中にあるとすれば、まず心の中の罪を清算しなければなりません。目が罪を犯すなら目をくり抜き、手が罪を犯すなら手を切ってしまえ、とイエスは峻厳なみ言を語るのですが、他人の罪に対しては寛容でした。「何度まで罪を許したらよいのでしょうか」というペテロの問いに、イエスは「七の七十倍まで許せ」と答えるのです。他人の罪に対しては、これを無限に許せということです。イエスに復讐という観念はありません。イエスは愛と許しの人であったのです。
聖書を読む私たちはイエスの奇跡の物語よりも、イエスの愛と許しの物語に,より感動を覚えるのです。そして聖書には、何人かの罪の女が登場します。
イエスとその弟子たちがガリヤラに行く道中、サマリヤを通過されたときのことです。サマリヤはかって侵入した異民族の子孫が住みついた地方で、異邦人のサマリヤと呼ばれて、ユダヤ人は避けて通るのが普通でした。
時は昼の十二時ごろでした。イエスは旅の疲れを覚えて、ヤコブの井戸と呼ばれる井戸のそばに座っておられました。弟子たちは町に食料を買いに行っていました。するとそこに、サマリヤの女が水を汲みにきたのです。イエスはその女に「水を飲ませてください」と声をかけました。女はぎくりとして、イエスに答えました。
「サマリヤの女のわたしに、どうして飲ませてくれとおっしゃるのですか」
ユダヤ人がサマリヤ人に、話しかけることはなかったからです。
「わたしが誰であるかを知ったなら、あなたは生ける水をもらったことでしょう」
「主よ、あなたは水を汲むものをお持ちになっていません。それに井戸は深いのです」
「この井戸の水を飲む者は誰でもかわく。しかしわたしが与える水の飲む者は、永遠にかわくことがない」
「水汲みにこなくてもよいように、その水をわたしに下さい」
「あなたの夫を呼びにいって、ここに連れてきなさい」
「わたしには、夫がありません」女はうつむいて、イエスに答えました。真昼の暑いさなかに、井戸に水を汲みにくる女はいません。彼女は人に隠れてそっと水を汲みにくる、いわゆる「罪の女」であったのでしょう。
「それはもっともだ。あなたには五人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。女よ、わたしの言うことを信じなさい。あなたがたが、この山でも、またエルダレムでもない所で、父に礼拝する時が来る」
サマリヤの女は、自分の事情をすべて知っているイエスに驚き、そんな自分を許して、話をしてくれるイエスの愛に感動したのです。彼女は町に行き、「あの人こそ、キリストかも知れない」と人々に伝えました。それでサマリヤ人は、ぞくぞくとイエスのもとに集まってきたのでした。
ヨハネが伝えるもうひとりの「罪の女」の話は、さらに感動的です。
律法学者やパリサイ人たちが、姦淫をした女をイエスのもとに引きつれてきました。
「先生、モーセは律法の中で、こういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか」彼らはイエスを訴える口実を求めていたのです。助けよと答えれば、律法に反することになります。殺せと言えば、民衆の反感をかうのです。
イエスは黙して、地面に何かを書いておられました。律法学者たちはイエスをせきたてます。イエスと姦淫をした女を人々はぐるりと取り囲んで、事のなりゆきを見守っています。
「あなた方の中で、罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」
やがてイエスは、人々に言いました。彼らは年寄りから順に、一人去り二人去り、ついには誰もいなくなったのです。イエスと、その女だけが残りました。姦淫の女の名はありませんが、彼女がマグダラのマリヤであったかも知れません。ルカの第八章では「七つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリヤ」と記されています。
いずれにしても、イエスの一行には弟子たちと共に「多くの婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物をもって一行に奉仕した」(ルカ8:3)のでした。男女関係に厳しいユダヤ社会にあって、イエスの一行は奇異な人々と見られていたに違いありません。
偽善者たち
イエスはまたマタイやレビ、ザアカイといった取税人にも「わたしに従ってきなさい」と声をかけます。取税人はユダヤ人が最もいみ嫌う人間でした。彼らはローマ帝国の手先となって、同胞から税をしぼり取る者たちです。彼らは豊かではあっても、ユダヤ人からは軽蔑され、罪の意識におびえていたのです。イエスは弟子たちと彼らの家で、食事を共にされることがありました。するとパリサイ人が言いました。
「なぜあなたがたの先生は、取税人や罪人などと食事を共にするのか」
パリサイ人とは一線を画された者であり、彼らは神との契約である律法を、絶対的に守る選民と自負していたのでした。ですから彼らは、取税人や罪人、異邦人とは決して食卓を共にしなかったのです。
「丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人である。わたしがきたのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである」とイエスは答えました。イエスは審く人ではなく、哀れみ愛する人でした。
パリサイ人らがイエスと対立した原因に律法があります。食事の前に手を洗うことは衛生上の問題ですが、これが律法となると神との契約です。手を洗わないで食事をすることは、神に背く行為ということになります。このように律法が細分化されて、律法学者という専門家が必要になったのです。律法を守ることは困難な事ですが、逆に外的に律法さえ守っていれば義人とされ、彼ら自身もそう思っていたのです。ここに律法の落とし穴があります。ルカの第十八章に、パリサイ人と取税人が祈る譬え話があります。
パリサイ人はこう祈りました。「わたしは貪欲な者、姦淫する者ではなく、取税人でもないことを感謝します。週に二度断食をし、十分の一を捧げています」
取税人は胸を打って祈りました。「神様、罪人のわたしをおゆるしください」
「神に義とされるのはこの取税人であって、あのパリサイ人ではなかった」とイエスは語るのです。罪を意識する者は、悔い改めることができます。しかし律法を守って自分の罪に気づかない者には、罪を清算する道がありません。彼は罪人よりも神に遠いのです。
律法の中でも絶対的とされるのが、安息日を守ることでした。安息日には仕事を休み、雑事に心を奪われることなく、終日神を思い、神に礼拝を捧げる日とされていました。ところが安息日には何もしないことが規則のようになると、それは形骸化してしまいます。
「あなたがたに聞くが、安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのと殺すのと、どちらがよいか」イエスはパリサイ人に問いかけます。彼らは安息日にしてはならない癒しをするかどうか、じっとイエスを見守っていたのでした。
「手をのばしなさい」イエスは言いました。その人のなえた手は、癒されたのでした。パリサイ人たちは激しく怒って、イエスをどうかしてやろうと相談し始めたのです。
祭司、律法学者、パリサイ人たちは、神が準備した選民たちです。しかし彼らは旧約時代の先入観に縛られて、新しい時代の訪れを知ることができませんでした。イエスの心中に、どれほどの無念の思いがあったでしょうか。彼らはことごとくイエスに対立して、大食いとののしり、病人を癒せば悪霊のかしらベルゼブルがやらせていると言ったのです。
「偽善なる律法学者、パリサイ人よ。へびよ、まむしのの子よ、どうして地獄の刑罰をのがれることができようか」イエスの怒りが爆発しました。しかし彼らはなおも、イエスに迫ったのです。
「先生、わたしたちはあなたから、しりしを見せていただきとうございます」
「邪悪で不義な時代は、しるしを求める。しかし預言者ヨナのしるしのほかには、何のしるしも与えられないであろう。ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるであろう」
地の中にいるとは、黄泉に下ることでしょうか。イエスは死を予感されていたのです。
「ニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたが、ヨナにまさる者がここにいる。ソロモンにまさる者がここにいる」
イエスが群集に語っているとき、弟子がきて告げました。
「母上と兄弟たちが待っておられます」するとイエスは答えて言われました。
「わたしの母とはだれのことか。わたしの兄弟とは、だれのことか」そして弟子たちの方に手をさし伸べ、「天にいます父のみこころを行う者は、だれでもわたしの母、またわたしの兄弟、姉妹なのである」
イエスは神の愛は語りましたが、家族肉身の愛を実感として、知ることはできなかったのです。父の愛を知らず、兄弟の愛を知らず、夫婦の愛を知らず、子を持つ親の愛を知らなかったのです。そして33歳の若さで、十字架で逝かれたのでした。
弟子たちを宣教に送る
1954年5月1日、「世界基督教統一神霊教会」が創立されます。文師は時に34歳でした。その翌年、多数の梨花女子大生と教授が入教、梨花女子大事件としてマスコミをにぎわし、大迫害が始まりました。文師は異端的信仰を理由に拘束されますが、三か月後には無罪となりました。それから師は弟子たちを、徹底的に教育し、訓練したのです。
1957年7月、夏期40日伝道が開始されました。弟子たちは片道切符一枚を手に、あとは何も持たずに任地に出発したのです。無一文で伝道に出発する弟子たちも命懸けですが、送り出す師も必死に祈られたのです。神とイエスが彼らを守り、導き、弟子たちは多くの霊的な体験をして、韓国各地に伝道の証しを立てたのです。
「このころ、イエスは祈るために山に行き、夜を徹して祈られた。夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び出し、これに使徒という名をお与えになった」(ルカ6:12)
イエスは徹夜で、何を祈られたのでしょうか。自らは死を決意され、天国実現の夢を弟子たちに託されたのでしょうか。マタイとルカでは十二使徒の名に多少の違いがあります。12数には多くのという象徴的な意味がありますから、必ずしも12人ではなく、もっと多数であったかと思われます。
「わたしがあなたがたをつかわすのは、羊をおおかみの中に送るようなものである。だから、へびのように賢く、はとのように素直であれ」(マタイ10:16)
イエスはイスラエルの各地に,弟子たちを宣教に送る決意をされました。銭も、ふくろも、つえも、くつも、二枚の下着も持たせず、弟子たちを宣教に送るイエスは、神に祈らざるを得なかったのでしょう。それは「天国は近づいた」という宣教の目的と同時に、弟子たちを訓練させ、霊的な体験をさせて、神を実感させる目的があったはずでした。
「語る者はあなたがたではなく、あなたがたの中にあって語る父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を殺すために渡し、また子は親に逆らって立ち、彼らを殺させるであろう。またあなたがたは、わたしの名のゆえにすべての人に憎まれるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる」(マタイ10:20)
これらのイエスのみ言は、実に恐ろしい内容です。キリスト教の歴史は、赤い血に染まる殉教の歴史でした。イエスのもたらす真理は天宙的理念、すなわち地上界と霊界を貫く真理であったのですが、地上の主権者はこれを許しませんでした。
「地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな、平和ではなく、つるぎを投げ込むためにきたのである。わたしがきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめと仲たがいさせるためである。そして家の者が、その人の敵となるであろう。わたしよりも父または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を愛する者は、わたしにふさわしくない。また自分の十字架をとってわたしに従ってこない者はわたしにふさわしくない。自分の命を得ている者はそれを失い、わたしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう」(マタイ10:34)
二千年前のイエスの言葉は、現代の再臨の時代にそのまま置き換えることができます。文師が提唱する統一運動は「親泣かせ原理運動」と言われ、家庭に平和をもたらすどころか、家庭を破壊するもののように思われてきました。まさに家の者が敵となり、親が息子・娘を拉致監禁する事件を起きています。歴史は繰り返すというより、天宙的理念と地上理念の衝突の、必然的な結果であると言えるでしょう。
さて、イエスの弟子たちの宣教は成功したのでしょうか。弟子たちは師から病を癒す霊力を授かったのですが、それも不十分なものであったようです。ある人は子供のてんかんを癒してもらおうと、弟子たちに頼んだのですが、彼らは悪霊を追い出すことができませんでした。イエスはその子のてんかんを癒しつつ、嘆きの言葉を口にされます。
「ああ、なんという不信仰な、曲がった時代であろう。いつまで、わたしはあなたがたと一緒におられようか。いつまであなたがたに我慢ができようか」(マタイ17:17)
イエスの苛立ちが、伝わってくるようです。弟子たちはイエスの天国理念を、まるで理解していなかったのです。彼らもまた、地上のことのみに捉われていたのでした。
「いったい、天国ではだれがいちばん偉いのですか」と弟子たちは、とんちんかんな質問を師にぶつけるのでした。イエスは幼な子を呼び寄せ、彼らのまん中に立たせて言われました。
「心をいれかえて幼な子のように、自分を低くする者がいちばん偉いのである」
奇跡と癒しを求めて群集は集まったのですが、御利益がうすれれば彼らは去ってしまうのです。また癒された者も、御利益だけを受けて去ったのです。癒された十人のらい者のうち、礼を言いに戻った者はただ一人でした。しかもそれはサマリヤ人であったのです。
「わざわいだ、ゴラジンよ、わざわいだ、ベッサイダよ。ああ、カペナウムよ、おまえは天にまで上げられようとでもいうのか。黄泉にまで落とされるだろう。さばきの日にはソドムの地の方が、おまえよりも耐えやすいであろう」
イエスはこれらガリラヤの町々に、のろいの言葉さえ浴びせるのです。彼らはイエスのみ言を聞いても、悔い改めようとはしなかったのでした。
洗礼ヨハネの死
獄中に捕らわれの身となっていた洗礼ヨハネは、ヘロデ王の命令によって首を切られてしまいました。ヨハネの弟子たちはその遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告しました。
「イエスはこのことを聞くと,舟に乗ってそこを去り,自分ひとりで寂しい所に行かれた」(マタイ14:13)とマタイは記しています。
イエスは追ってくる群集から逃れ、ひとり寂しい所に行かれ、おそらくは泣かれたことでしょう。そしてヨハネのために神に祈ったのです。
イエスは孤独でした。群集に囲まれ,弟子たちが彼を取り巻いていたとしても、イエスを真に理解する者はひとりとしていなかったのです。「友のために命を捨てるより大きな愛はない」と語ったイエスでしたが、彼のために命を捨てる真の友がいたでしょうか。ひとりもいなかったのです。イエスの生前の弟子たちは無知で弱虫でした。後のパウロのような、学問と知識のある弟子はひとりもいませんでした。
洗礼ヨハネが命を捨てる覚悟でイエスの友となり,イエスと一体になったならば,イエスの生涯は十字架に向かうことはなかったのです。
ヨハネは獄中から弟子をつかわして、「来るべきかたはあなたですか、それとも他に待つべきでしょうか」と問うています。ヨハネの弟子が何と報告したかは不明ですが、イエスの奇跡のわざを伝えたことでしょう。もしヨハネが出獄したなら、今度こそイエスの証し人として、メシヤの道を直くしたことでしょう。しかしイエスは今、洗礼ヨハネの死の報告を聞いて、その希望がすべて消え失せたことを知られたのでした。
およそ五千人がいたとマタイは記していますが、それは誇張としてもかなりの群集が集まっていました。イエスは五つのパンと二ひきの魚を取り、これを祝福して人々に与えました。すると群集はすべて満腹して、なお十二のかごいっぱいに余ったのでした。これが給食の奇跡です。文字どおりに信じるもよし、霊的に満たされたと見ることもできます。
イエスは群集を解散させてから、しいて弟子たちを舟に乗せて向こう岸に渡らせたのです。そして祈るために、ひそかに山に登ったのでした。夕方になっても、ただひとりでそこにおられました。
弟子たちが舟で帰ろうとすると、逆風が吹いて海が荒れました。すると夜明けの四時ごろ、イエスが水の上を歩いて来られたというのです。マタイは「あなたは神の子です」と弟子たちに言わせています。マタイは奇跡物語によって,イエスを神格化しようと試みているのですが、ヨハネはイエスのみ言として、哲学的な内容をもたせています。
「わたしは天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者は、いつまでも生きるであろう。わたしが与えるパンは,世の命のために与えるわたしの肉である」(ヨハネ6:51)パンは単なる食物ではなく、ここでは霊的な意味に使われているのです。
「どうして自分の肉を食べさせることができようか」と人々は呟いたのでした。
「人の子の肉を食べず、また、その血を飲まなければ、あなたがたのうちに命はない」
イエスのみ言は群集には理解できませんでした。いや群衆だけではなく、弟子たちにも理解できなかったのです。弟子たちの多くは「これはひどい言葉だ、だれがそんなことを聞いておられようか」と言ったのでした。
「それ以来、多くの弟子たちは去っていって、もはやイエスと行動を共にしなかった」(ヨハネ6:66)とヨハネは記しています。
「あなたがたも去ろうとするのか」
イエスは苦しげに,十二弟子に問いかけます。その中には師を裏切ることになるユダもいました。ペテロは師を慰めるかのように、こう答えたのでした。
「主よ、わたしたちは、だれのところに行きましょうか。あなたを信じます」
サタンよ引きさかれ
「人々はわたしを、誰と言っているか」イエスは弟子たちに尋ねました。
「洗礼ヨハネだと言っています。また他の人はエリヤだと言い、あるいは古い預言者のひとりだと言っています」弟子たちは口々に答えました。
「では、あなたがたは、わたしを誰だと言うのか」
「あなたこそ,生ける神の子キリストです」とペテロが答えました。
「バルヨナ・シモンよ、あなたはさいわいである。あなたはこの事をあらわしたのは、天にいますわたしの父である。あなたはペテロである。わたしはこの岩の上に,教会を建てよう。わたしはあなたに天国の鍵を授けよう」
イエスを最初にメシヤとして証したのは洗礼ヨハネでしたが、キリストの主弟子の座はペテロに奪われたのです。後にペテロが殉教することになるローマの教区長が,天国を鍵を握る法王の座についたのでした。
イエスは、自分がキリストであることを誰にも言ってはいけない、と弟子たちを戒められます。なぜでしょうか。弟子たちに,洗礼ヨハネのような権威がないからでしょうか。エルサレムから送られた律法学者やパリサイ人は、イエスとその弟子たちを常に監視していました。彼らはイエスを捕らえる口実を捜しまわっていたのです。弟子たちが師をメシヤだと公言したなら、災いは彼らにも及ぶであろうと、イエスは案じられたのでしょう。
この時から,イエスはご自分の運命を弟子たちに告げられます。必ずエルサレムに行き、多くの苦しみを受け,祭司、律法学者たちから捨てられ,殺されて、そして三日目によみがえるべきことを示されたのでした。
するとペテロは,イエスをわきに引き寄せて,師をいさめ始めたのです。
「主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはずがございません」
イエスは振り向いて,激しくペテロを叱責されました。
「サタンよ,引きさがれ。わたしの邪魔をする者だ。あなたは神のことを思わないで,人のことを思っている」(マタイ16:23)
イエスの叱責は,ペテロには意外なことでした。ペテロを始めとして,弟子たちはまだイエスに希望を抱いていたのです。モーセのような奇跡を見せるメシヤの夢を、弟子たちは捨てきれなかったのです。ユダヤ教のメシヤは不滅であり,十字架にかかって死ぬメシヤ像はありません。
主をいさめるペテロを,「サタンよ引きさがれ」とまで叱責されたことを見れば,イエスの十字架への道は,最初から神の予定であったようにも考えられます。師の死を防ごうとする弟子を、イエスはなぜサタンと呼ぶのでしょうか。
まず第一に、地上の主管者はサタンであるということです。サタンはこの世の君,この世の神です。地上の人間はサタンの手のうちにあるのです。天の父はサタンの手の中でもだえ苦しむ人間を、救い出す責任があります。しかし無形の主体である神には,手も足もありません。神の代身としての、肉身を持つ神の息子がいなければなりません。神は時が至って、地上にメシヤを送られました。それが神の独り子,イエスです。
イエスをメシヤとして証しする,地上の堕落人間の代表としての中心人物が必要です。それが洗礼ヨハネでした。しかし彼は、その責任を全うすることができませんでした。
かくして神が準備された選民の、その指導者たちはイエスを弾劾する側にまわったのです。イエスに従った弟子たちは無学な漁師,民衆に嫌われる取税人や罪人たちでした。
奇跡と癒しを求めて,一時は大勢の群集が押しかけたのですが、彼らは蜜がなくなった蟻のように去ってしまうのです。わずかな弟子たちだけがイエスの優しさにひかれ、また自分たちの夢を捨てきれずに従ってきたのです。イエスはひとり神に祈り、神のみこころに従う決心をされたのです。地上において神の国を建設する,第一のみ旨は失敗に終わったことを、イエスは認めざるを得なかったのです。
しかし、もしもイエスが十字架の道を避けて、どこかへ逃亡したらどうでしょうか。今日私たちはイエスの名を知ることもなく、キリスト教は地上に存在しなかったのです。そしてイエス以後の歴史は、もっと悲惨であったかも知れません。それこそサタンの願いであったのです。ですからイエスは、「サタンよ引きさがれ」と叱責されたのです。
イエスの十字架への道は、あくまでも二次的な路程であったことを,忘れてはなりません。イエスは霊的に復活して,霊的な勝利は果たされましたが、肉身の救いは未完成なのです。つまり地上に神の国を建設するみ旨は、未だ成就していないということです。イエスは霊界で常に祈っておられ、二千年の間クリスチャンたち導き、再臨の時を待ち望んでこられたのです。
イエスの十字架への道は、変貌山の三者会談において、正式に決定されたのでした。
(第七章へ)